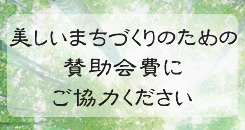私の散歩(八) 小田 敏夫
六甲で喫茶店を営む友人がいる。十数年来の音楽仲間であるが、親しく付き合うようになったのは、彼が会社勤めを辞めて、自分の店を持ってからのことである。
その友人と、昨年の夏から「珈琲の旅」を始めた。神戸や京都のちょっと氣になる喫茶店を、一日かけて数件ずつ巡る小さな旅である。旨い珈琲を飲みたい男と、旨い珈琲を入れたい男の二人旅は、すでに四度を数える。
街の喫茶店は、その設えも、そこで供される珈琲も、どれひとつとして同じものがない。そこに集う人の顔も違う。店と珈琲と人とが醸し出す、様々な雰囲氣を楽しむのである。
旅の後にも楽しみがある。それは、ひとつの旅を終えるごとに、友人の入れる珈琲の味が変わっていくことだ。その変化に私が氣付くのを、彼もまた楽しみにしているようである。
週に一度、友人の店を訪ねる。大抵は土曜の夜である。私にとって、そこで週末のひとときを過ごすのは、一週間の「シメ」であり、生活のリズムとなっている。
五十路半ば、私のような年代の人間には、青春は喫茶店と共にあった、と言ってよい。
高校生の頃、黒い詰襟の学生服で、学校すぐそばの喫茶店に初めて入ったときのこと。店に通じる地下への階段を降りながら、氣分は逆に高揚していった。少し背伸びをしたような、ちょっと不良になったような、妙な心のざわめきを、私は未だにわすれない。
大学に入ってからは、日に二度三度、喫茶店通いをした。喫茶店全盛時代、広島の実家の半径数百メートルの範囲内に、思い出すだけでも、軽く十軒以上の店があった。
毎日のように通う店もあったが、その時の氣分で店を選んだ。大概は仲間と一緒で、遠くの店にはドライブがてら車を走らせた。その道中がまた楽しいのだった。
お金が無くてもコーヒーが飲めた。アルバイトで懐の暖かい誰かが、勘定を持ったからである。三十年以上経った今も、昔の仲間に会うと、コーヒー代の割り勘はない。
あの頃は、喫茶店に行くこと自体が目的だった。そこで頼むのは、とりあえずのコーヒーであって、それを特に味わって飲むという氣持ちは、あまり無かった。
そんな、味に頓着の無かった当時でも、『旨い』と思った珈琲がある。広島から神戸に遊びに来たとき、神戸の叔母が連れて行ってくれた、トアロードの喫茶店の珈琲である。その香りと味。濃くて深く、苦くて甘い、珈琲の魅力の全てが、カップの中に注ぎ込まれていた。その、言わばフルボディーの味わいが、それ以降、「私の珈琲の味」となった。
二十代の後半、合氣道修行で東京に住んでいた頃も、修行が明けて広島へ帰ってからも、時間を作っては、その店に通った。残念ながら、今はもうその店はないが、縁とは不思議なもので、神戸に住むようになってから、その店のオーナーと知り合い、今でも親しくしてもらっている。
私は、旨い珈琲を出す喫茶店のある街は、その街の文化度が高いのだと思っている。
ずっと舶来文化の入口だったミナト神戸の珈琲が旨いのは当然のことだ。古都京都然り。京都には、茶の湯の文化もある。
「私の珈琲の味」は神戸のそれだが、京都のそれもまた味わい深い。珈琲の味は、街の歴史や個性、そしてそこに暮らす人々の姿を、そのまま映し出すのである。
岡本の街にも旨い珈琲がある。私の知るある店主は、まだ若いけれど、すでに相当の研鑚を積み、今なお身銭を切って修行に励んでいる。飲むならこういう珈琲だろう。
岡本には、店先を花や緑で飾る喫茶店も多い。味の追求に店の装い、各々方向は異なるが、そこには、凡そマニュアルにはない、人の氣持ちが込められている。それこそが街の喫茶店の良さであり、そんな店があればこそ、岡本の魅力も弥増すのであろう。